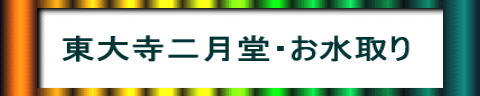
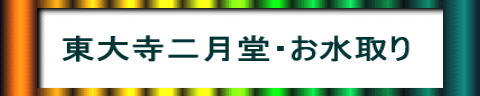
東大寺二月堂の「お水取り」は、旧暦二月(現在は3月1日から14日)に
おこなわれることから正しくは修二会(しゅにえ)といい、
奈良に春を呼ぶ行事として広く知られています。
2003年3月3日、2006年3月11日、2回「お水取り」に行ってきました。
その時の写真を元にまとめます。
まず動画をご覧ください。

![]() お願い: PCによっては動画の起動がうまくいきません。
お願い: PCによっては動画の起動がうまくいきません。
その時はお手数ですがホームに戻って、もう一度このページに入ってください。
不思議なことですが、動画が見えます。
お水取り 東大寺二月堂の「お水取り」は、旧暦二月(現在は3月1日から14日)におこなわれることから正 しくは修二会(しゅにえ)といい、奈良に春を呼ぶ行事として広く知られています。 「お水取り」の名で知られる二月堂の「修二会」は東大寺の僧 実忠(じっちゅう)が752年に始め たもので、正式には「十一面悔過法(けかほう)」と呼ばれています。十一面悔過法とは、日常犯 している過ちを本尊の十一面観音の前で悔い改めることをいいます。 この「修二会」は、2月20日の別火(本行のための準備期間)入りから3月15日の満行にいたる 約1か月に及ぶ法要で、752年に始められてから、今日まで1250年以上もの間、一度も休むこ となく行われてきました。 「お水取り」では、身心の穢れを払った練行衆(こもりの僧)と呼ばれる僧侶たちが、本尊十一 面観音像の前で観音の宝号を唱え、五体投地などの荒行を行うことで罪障を懺悔(ざんげ)し、 「天下泰平」「五穀豊穣」「万民快楽(ばんみんけらく)」などを願って祈りを捧げます。 練行衆が上堂するとき、足元を照らすために大きな松明をかかげる「おたいまつ」は、「お水取 り」の代名詞にもなっています。 二月堂の内陣には、奈良時代に造られたといわれる大小二体の十一面観音像が安置されてい ます。「お水取り」においては、3月7日までが大観音、8日以降が小観音と、本尊が途中で交代 しますが、大観音、小観音はいずれも、練行衆といえども拝することのできない絶対秘仏になっ ています。 「お水取り」は「閼伽井屋(あかいや)」の中にある「閼伽井」(別名、若狭井)から汲まれる香水 (こうずい)を本尊十一面観音に供えることに由来します。 詳しくは: (見学の仕方の注意点がよく分かります) (本行中に二月堂の本尊、十一面観音に椿の造り花をささげます。その椿の花びらに 使われる紅花で染めた紙と、お水取りの様子を案内してくれます) |
 |
「二月堂」の真下、芝の斜面に「良弁杉」が、植わっている。良弁僧正が2歳の時、ある日突然大鷲にさらわれ、杉の木のてっぺんに置き去りにされたという言い伝えがある。杉はかつて樹齢約600年、高さ7丈の巨木であったといわれているが、昭和36年9月11日第2室戸台風で倒れ、今はその三世。 良弁僧正は、日本に華厳宗をひろめるとともに東大寺の創建に大いに力を尽くし、東大寺の初代別当となった。 奈良の昔話:二月堂・良弁杉 (NDA) |
| 練行衆が修二会の間着る衣。紙で作る。 仙花紙という強い紙を棒に巻き付け竹の輪で何回もしごいて柔らかくして、寒天を塗る。約40枚を張り合わせ反物にし、木綿の裏を付けて袷(あわせ)にする。 紙衣は清浄視され、座るときは必ずテシマゴザの上に座らなければならない。 これが修二会の終わりの頃には松明などのすすで黒くなり、荒行によって破れたりしている。 (色の万華鏡HPより) |
 |
| 東大寺二月堂・お水取りで使用された紙衣 阿波和紙伝統産業会館(徳島県吉野川市)所蔵 |
2003年3月3日 「お水取り」3日目の見学に行ってきました。 小雨に煙る東大寺境内の様子も撮ってきました。 ウェブリアルバムのスライドショーにまとめました。 2003・お水取り このアイコン(写真)  をクリックしてご覧ください。 をクリックしてご覧ください。 |
2006年3月11日 「籠松明」を明日に控えた11日、「お水取り」に行ってきました。 2回目の見学です。 食堂(じきどう)の壁際に「籠松明」が立てかけられていました。 ウェブリアルバムのスライドショーにまとめました。 2006・お水取り このアイコン(写真)  をクリックしてご覧ください。 をクリックしてご覧ください。 |
ホームへ
(2007.01.29作成)